プライベートバンキング資格を超高速で取得しようと思う。(1カ月でプライマリーバンカー)
このシリーズでは、プライベートバンキング(上巻、下巻)を通して学んだ概要を整理しておく。
古い教科書がベースとなっているが、本質は変わらないと思うので、プライベートバンキング資格を取得する方の助けになればと思います。
ぶっちゃけ何がポイントなのか、感想も交えて整理します。
はじめに プライベートバンキングと日本の現状
基礎知識体系は7項目ある。既にわからない単語があるが、詳細は後程見ていく事にしよう。
①リレーションシップ・マネジメント
②ウェルスマネジメント
③不動産
④税金
⑤信託・エステートプランニング
⑥マス富裕層
⑦職業倫理
PB業務とは下記のようです。
「富裕層の資産の保全ならびに効率的な次世代への承継を支援するための、金融資産の運用を中心とする包括的な個人金融サービス」
プライベートバンクは、もともとスイスの銀行で提供されている秘密口座のイメージなどが広まって、富裕層向け金融サービスとして国際的に広く認知されたらしい。
日本においてプライベートバンカー資格(プライマリー、シニア)を保有している方は、2,246名(2024/9月末現在、日本証券アナリスト協会より)らしい。いがいと少なく、希少な資格の様子。
もともと、海外と比較して広がりにくかったようで、マス富裕層多すぎ、税制や土地制度が複雑、金融業務や業法得・規制が複雑、金融機関で専門人材育ちにくい等、ざっくりいうと、サービス提供するの難しい割に顧客が少ないっていう、ビジネスがなりたちにくい環境であったようです。(そこは今も変わらない気がしますが。。。)
ただ、今後は1500兆円の個人金融資産の大半が高齢者に保有されているので、何とかしないといけないという事で、PBの重要性が高まり、「富裕層(マス富裕層含む)のために、投資政策書なるものを作成し、伴走し続ける役割」として、プライベートバンカーが求められているようです。
・富裕層:住居等を除く投資可能資産1億円以上(100M$以上)
・マス富裕層:資産1000万円~1億円未満(10M~100M$未満)
※円安だけど、円換算で100円=1$で計算、キャップジェミニの基準を採用
1.RM(リレーションシップ・マネジメント)
顧客との基本的なアプローチ手法と留意すべき事項について理解出来る内容となっています。
1-1. 顧客を知る
まずは現状把握して、先方のニーズを知ろうということで、資産を形成した経緯を聞きながら、ラポールを形成すべきとのこと。マネーロンダリングも分かり、まずは顧客の基本情報を把握する事から始めたい。
次に事業や投資の基本的な考え方や哲学を聴くために、HP等での会社の沿革を把握しながら、投資の好み、リスク許容度、買収などの意思決定の判断基準についてヒアリングし、基礎情報を得ておく。
①資産の現状は?
主に確認するのは下記。
・経常資金収支(資金繰り等大丈夫?)
・資産・負債の把握(資産あるよね、資金繰りも大丈夫よね?)
・資産の保有形態の把握(タックスプランニング適切?流動性リスクや予想外の評価損ある?等)
②人生で何したいの?お金使って何したいの?
・人生で結局何をしたいねん?
・お金で買えるものは限られているから認識してね。愛情、友情、健康、仕事などのもたらす非金銭的報酬は買えないから認識して、大事にしてね
っていう事を確認したい。
プライベートバンカーとしては、3つのCの役割を求められるらしい。正直いって、かなり高度な役割を求められている。もはや人生の重要な相談相手だ。。。
Counselor:ライフデザイン
Consultant:ファイナンスプランニング、インベストメントプランニング、金融商品選択、見直し
Coach:資産形成の伴走者
また、色々な懸念について聞く必要があり、家族や扶養の責任、健康、家族の問題、子供や孫の教育、後継者、財産上の課題 等を気にしながら、将来の夢に向かった対応を考える事を支援する。
1-2. 自己を知る
ここでは、プライベートバンカー自身や所属する組織の強みを整理する。
SWOT分析で把握することが書籍では推奨されている。自身を例に、プライベートバンカーとしての要素を少し考えてみたい。
強み:
日々の生活費を抑えながら、メリハリをつけた満足度の高い支出管理が出来る。
大手日系および外資での十数年のコンサルティング経験を元にしたナビゲーションや伴走支援が出来る。
コーチングによる人材育成やサポート実績を元にしたコミュニケーションが出来、プロコーチとしての専門的な教育を受けている。
金融機関や組織にとらわれない、顧客に根差した提案や伴走支援が出来る。
ITガバナンス、ITマネジメントの分野において、国内トップレベルのアドバイスも出来る。
大手日系や外資コンサル、高学歴なキャリアを歩んでおり、アドバイスが出来る。
金融資産運用や証券分析は、一通りの知見を保有しており、目利きも出来る。
弱み:
金融機関で働いた経験がないため、プライベートバンカーとしての経験が少ない。
シニアPBや専門の金融担当者と比べると、幅広い知識で見劣りする。
機会:
・大手企業や専門のPBあまりサポートしないであろう大手日系や外資系企業等でサラリーマンをし、一定の財産を築きはじめた方(相続や個人で一定の資産を築けたが、運用等の知識がない方で、資産規模も数千万円~数億円規模の方)
・コーチングやコンサルティングのプロフェッショナルからアドバイザリーを受けたい方
・金融とは異なるバックグラウンドの経験を望む方
・雑談しながら気軽に会話する事を望む方
脅威:
金融の専門知識や事例を保有する大手企業参入
Youtube等の無料メディアにおけるサービスによる代替
同じような個人PBの参入
自分の相対的な強みを把握するのには下記観点でみるのがよいとのこと。確かにお客様がいて、収益性の高いサービスを提供出来れば強そうだ。
・顧客基盤:PBとしてはまだないから、獲得コストを大分かけねばです。PBとしての認知度や評価がないので、うまく作らねばです。ここが大分弱いので、営業・マーケティングについては考えないとです。
・サービスの質:コンサルタントやコーチとしての経験は豊富かつ、課題解決に向けた提案力はあるし、金融関係の知識であれば調べればすぐにわかるので、満足のいくサービスを提供出来る自信あり。何より、PBというサービスが凄く好きそうなので、よいサービスが提供出来そう。
サービス面では、メニューやコンテンツをしっかり充実していく必要があり、サービス内容も顧客が安心してうけてもらえるようにしておく必要がある。サービス自体はロジカルに、納得感のあるものに仕上がるように、ベースとなるコンテンツや進め方、作業はあらかじめ整理しておきたい。
エージェントAIを活用しながら、クイックに質の高いサービスが提供出来るように事前準備はしておき、提案につなげたい。
・収益性:コンサルティングサービスを軸にすれば、収益性は確保出来そう。ツールなども豊富に用意して、使えるようにしておき、クイックに提供できるようにしておきながら、GenAIも駆使すれば、さらに収益性の高いサービスを提供出来そう。
顧客ロイヤリティのマネジメントでは、LTVの考慮が重要。リテンション、口コミ、クロスセルやアップセルをしながらLTVを高めたい。特にこの最初の顧客獲得費用を少なくするのが重要だ。
・顧客獲得費用
・基準利益
・購入増加による利益
・オペレーティングコスト低下による利益
・口コミ紹介による利益
・価格プレミアムによる利益
自身の弱点を補完するためには、社外の知見、露出、外部のお墨付き、ノウハウの蓄積、Giveの精神が求められる。
トップアドバイザーリストやノウハウリストを作って、提供するという事は有効らしい。これは、自身の人生においても持っておくと有用そうだ。棚卸も含めて考えてみるのがよさそう。
ここでは、PBとしての生産性を把握するための各種指標を整理する。
・預かり資産残高
・一人当たり目標営業利益
・直接/関節経費の把握
・取引の直接経費
・直接/間接人件費
・部門別管理費
・全社共通管理費
自身の時間コストについても整理しておきたい。完全週休2日だと、大抵の場合は1,864時間/年、一人当たり売上目標が60百万円だと、時給で32,188円を稼ぐ必要がある。
ここから、現実的な営業プランを考えていく事が推奨されている。
また、潜在的な顧客ニーズに対応出来るように準備しておくことがPBには必要である事が述べられている。自身のコンサルティングビジネスにも通じるものがある。クライアントビジネスに関わる情報源やソリューションは多数持っておきたい。
・外部の専門チーム:法務、税務、不動産、保険、信託、銀行業務、医療、留学等の富裕層向けサービスの紹介
・外部専門家とのコミュニケーション:専門用語や基本的な提案テンプレートの準備
・顧客との橋渡し:クライアント内部とのコミュニケーションやクライアントへの説明、交渉等
PBには、単なる専門家ではなく、総合的に信頼できるアドバイザーとしての役割が求められるので、そこを目指す事は忘れないようにしたい。
1-3. 顧客との効果的な関係を築く
有力顧客を作り、そこから紹介してもらい、クライアントを増やしていく必要がある。この際、顧客からの紹介を引き出すには、クライアントのビジネスを支援し、紹介してもらう方法がある。
・クライアントコアビジネスへの貢献(お客様の紹介)
・コスト削減の提案(電力、福利厚生、出張 等)
・幹部人材の紹介(マネジメント層の知見が往々にして不足)
また、コアビジネス以外でも顧客の期待を超えるサービスは存在するので、あわせわざで提供出来るようにしておく必要がある。
・有力顧客から紹介を受ける
・子供の就学、有名小学校の親や教室などの紹介
・就職、結婚の支援
・困難な会員制クラブの会員権取得
・社長スピーチの作成、英語等
・顧客紹介への感謝を工夫する。
・会員組織とネットワークを活用する
・社交クラブ、高級スポーツクラブ、名門ゴルフクラブ、有力な財界人や学者店政治家の集まる勉強会系の会員組織
・効果的なメンバーシップの活用(ボランティアや事務、コミュニティ等)
顧客への意思決定には、様々な阻害要因を除く必要がある。特に顧客が心理的に購買時に感じる心のハードル4つは留意し、サービスを提案する時は、常に意識するようにしたい。
・不信のハードル:会社名、実績、書籍、講演 等で信用を補強
・不要のハードル:顧客の話をちゃんと聞いて、提案
・不適のハードル:解決策のフィット感を理解してもらうために、セカンドオピニオンや関係者の説得が重要
・不急のハードル:今やらないとねっていうのを示す。これが一番難しいやつですね。
書籍の残りの部分(RMの章)は、ケースを中心に意思決定の阻害要因の取り除き方や顧客管理の技法、ターゲット別の財務課題とアプローチトーク、効果的な顧客コミュニケーション手法の確立について述べられている。
PBに即してはいるものの、本質的には営業が行う業務と変わらない。詳しくは本書を見てほしい。
最後に(感想)
今回は、リレーションシップマネジメントについてみてきた。コンサルティングビジネスでも生かせる考え方が多く、実際のビジネスでも同じような考え方を横展開出来そうなので、時間がある時に自分の考えを整理するとよさそう。
PB資格だけでなく、実ビジネスでもあらためて勉強になるポイントがあってよかった。

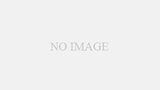
コメント