お酒依存が止められない問題
社会人になれば、増えてくる「お酒」の量。令和の時代になって、お酒を断りやすくなったとは言え、懇親会や会食などは変わらずあるため、お酒を飲む機会は依然としてある人が多い。
そのうち、仕事でのストレス解消や、お祝い事等で、プライベートでも飲む機会が増え、いつの間にか酒量がどんどん増える事に。そのうち、翌日にも影響を与える程飲むようになり、飲みすぎた機能を後悔するようになる。そのうちだんだんとお酒の量も頻度も増え、やめられなくなっていく。。。
なんとなく、お酒が体に悪そうだとわかっていてもやめられないお酒。多くの方は、断酒を決意したり、量を減らそうとはしているものの、やめられない人が大半なのではないだろうか。そのうち、やめられない事を肯定しだし、「いやそもそもストレス解消にもなるし、気分もよくなるからいいかな」なんて思い出して、変わらない日々を繰り返してしまいがち。
そもそも、お酒とはなんなのか、どのようなメリットとデメリットをもたらすのか。なぜお酒をやめる事が難しいのかを考え、お酒との付き合い方を考えるポイントについて考えてみたい。
そもそもお酒はいつから飲まれるようになったのか?
はじまりは紀元前4000年前の果実酒が最初。ビールは紀元前3000年前で、日本酒が出来たのは8世紀頃(奈良時代)、庶民が簡単に飲めるものではなく、正月や慶事などで飲んでいた。その後、鎌倉時代から江戸時代に庶民にも普及し、一般的に楽しまれるようになった。
16世紀から19世紀にかけて、ワイン、ビール、ウィスキーが日本に伝わり、明治維新以降、欧米諸国の先進文化を体現する酒と認識され、豊かな生活の象徴、憧れとして飲まれるようになっていったとのこと。
ちなみに、もともとヨーロッパでは、地上の水が飲用に適さないものが多かったらしく、アルコールが安全だという事で飲まれていたらしい。その後、非アルコール飲料が普及していったようです。
なぜ、お酒を飲むのか?
最初は付き合いだったり、誰かに勧められたりして、お酒を飲み始める事が多いと思う。人生を過ごす過程で、何度もお酒を飲んでいくうちに依存性が高まると同時に、良い体験(機嫌がよくなる、ご飯がおいしい(お酒の席にはおいしいご飯がつきもの)、うれしく・楽しい(大抵はお祝い事だったりでお酒がふるまわれるので))や好感が持てるイメージ(バーでかっこよく飲むドラマの主人公、高級ワイン片手に発信するYoutuber、仕事終わりに缶ビールをおいしく飲むCM 等)が重なって、お酒を飲む事がポジティブなものに変わり、はまっていく人が多いのだろう。
単純に飲みたいから飲むっていう事だとは思うのだが、なぜお酒を飲むのか分解して考えてみたい。
- お酒自体がおいしい、好き
- 食事をおいしく味わいたい(お酒と食事が合う)
- 特別な雰囲気を味わいたい
- お酒を飲んでいる自分が好き
- リラックスをしたい
- お酒を飲むと楽しい気分になれる
- お祝いをしたい、お祝い気分を味わいたい
- 食欲を高めたい
- 嫌な気持ちを解消したい
- 付き合いで飲まざるをえない
- 血行がよくなる
- 便秘がよくなる
- 飲まずにはいられない(お酒依存により) 等
コミュニケーションが円滑になるとか、一部健康にいいといった記事も見つかりはするが、個人的にあまり実感できなかったので、割愛する。
ここで気を付けておきたいのが、お酒特有の依存性については、動機として強い割に、個人に直接的なメリットをもたらさないので注意したい。この「酒依存」というものが結構なウェイトを占めて、人生の満足度に繋がらない酒の頻度や量を高め、お酒を飲むことによる後悔の大半を占めているのではないかと思う。そのため、個人的な動機として抑えようがない、デメリットが出やすいお酒依存による飲酒(なんとなく飲んでしまう、飲みたくなってしまう状態)をなくすために断酒に取り組み、上手に付き合っていく事を中心に考えていきたい。
なぜ、お酒は飲むとよくないのか?
お酒は合法で、あれだけCMで流しているから安全だ、皆飲んでるから大丈夫だと思っている人は多いと思う。はたして本当にそうだろうか。
既にお酒は健康にとって、害しかないという結論も出されている程、体によくないものと思われつつある。それでは、どのようなデメリットがあるのかを見てみたい。
①健康・体力を害する
- 健康を害する、体力が衰える(太る、肝機能低下 等)
- 疲れる、疲れやすくなる
②病気になる
- あらゆる臓器に被害を発生させるリスクが高まる(肝障害、脳機能障害等)
- 急性アルコール中毒になる
③精神的に弱くなる
- メンタルが不安定になる
- 精神疾患になる(認知機能や抑うつ)
④頭が悪くなる
- 脳が委縮する(しかも戻らない)
- 仕事のパフォーマンスが下がる(寝ても脳が休まらないため)
⑤金銭的負担が大きい(5,000円(1,000円~数万円)/1回)
- お金がかかる
⑥時間を無駄にしてしまう(半日~1日/1回)
- 翌日気分が悪い時間を過ごす
- まともに過ごせる時間が減る
⑦周りに多大な迷惑をかける(飲まない人は不快に思っている人も多い)
- 事件や事故を起こす可能性がある(ハラスメント等含む)
- コミュニケーションが乱暴になる
- 問題行動を起こす
冷静に考えてみると、人生に甚大な悪影響を及ぼす可能性があり、かつデメリットは大きいと思うが、それでもやめられない人が大半だと思う。それでは、なぜお酒をやめる事が難しいのだろうか?
なぜ、お酒を飲んでしまうのか?
明確な理由がない限り、飲酒量や頻度をあげてしまう最大の原因は、お酒が持つ依存性や耐性(飲めば飲むほど効かなくなる)にあると思う。特に二杯目や三杯目以降は、コントロールがしにくくなるのではないだろうか。それでは、健康にお酒と付き合うためにも、断酒を実現するためにも考える必要のある、お酒の依存について考えてみたい。
お酒に含まれるアルコールは、依存性薬物となっており、たばこに含まれるニコチンよりも、身体依存および精神依存の高いものと認識されている。
精神依存のレベルであれば、シンナーや大麻、LSDと同等もしくはそれ以上であり、身体依存のレベルであれば、シンナーやコカインよりも依存性が高いと言われ、覚せい剤や大麻、LSDなどは、そもそも身体依存しない薬物と言われている。これだけみると、一般的に知られている薬物と比べて、なかなか依存度の高いものがアルコールという位置づけになっている。
※精神依存:欲しいという欲求が我慢できなくなること
※身体依存:薬が抜けると、手足の震えや幻覚、意識障害など離脱症状(禁断症状)が起きる事
ちなみに薬物による悪影響については、①脳や心、体がめちゃくちゃになる。②自分の意志ではとめられなくなる、③凶悪な事件を起こす、④友達や家族を失う と厚労(pamphlet_01a.pdf)HPに記載があり、正直お酒飲んでても確かにそういうのあるよねっていう感じ。
さて、とにかくそんな依存度の高い薬物である「アルコールの依存」から脱却するのは難しく、社会生活を営む上では、確実に飲む機会が定期的に発生するアルコールをやめるというのは至難の業であるものと認識した方がよさそうである。
お酒とどのように付き合うべきなのか?
今まで見てきたように、正直一般的に知られている薬物並みに全く摂取しない(お酒を飲まない)方が、頭にも心にも体にもよさそうなものではある。一方で、人によっては一定のメリットを感じる場合もあり、また飲まざるをえない機会もあるので、正直断酒をする事自体は難しい人が多いのではないだろうか。
それでは、断酒もしくは少なくとも飲む量や頻度を完全にコントロールする事は出来ないものだろうか?お酒とちゃんと付き合う事で、最大限のメリットを享受するために、飲酒をコントロールする方法を考えたい。
まずは、どのレベルでお酒と付き合うべきかを考えたい。これはどれがいいとか、悪いとかではなく、人生において、お酒をどのように位置づけるかという事になる。
- (レベル1)完全な断酒を目指す
最もわかりやすいのが断酒だが、このレベルを目指すのは正直困難だろう。いくつものハードルが存在し、強力な自制心がなければ、達成する事は難しいだろう。少なくともお酒の付き合いはかなり多い状況なのではないか。お酒を飲む機会やお酒が好きでない方は比較的問題ないだろうが、お酒に悩まれている方はそうではない人が大半だと思うので、そういった方において問題が発生する場面を考えてみたい。
とにかくお酒を飲む機会は多く、その日の気分で考えていてはとても飲酒欲求を抑える事は出来ないだろう。
①特定の人と飲む機会があった時
・友人等との飲み会をどうするか
・仕事上の飲み会(クライアント、社内)をどうするか
・家族での外食時にどうするか
・親族との食事時にどうするか
・普段の家での食事時(主に夜)にどうするか
②特定のイベントで飲む機会があった時
・催事・イベントがある場合にどうするか(お祭り、オクトーバーフェスト、試飲会 等)
・冠婚葬祭時にどうするか
・旅行時にどうするか
③外敵にお酒を飲むきっかけがあった時
・お酒のもらいものをした時にどうするか
・無料の試飲会で進められた時どうするか
④感情の起伏があった時
・ストレスを大きく抱えた時にどうするか
・逆にうれしい事があった時にどうするか
⑤飲み物として飲みたくなった、我慢できない(依存)時
・とにかく飲みたくなった時
・スーパーやコンビニ、CM等、お酒を見た時にどうするか
少なくとも、これらの場面で飲酒欲求を抑える事が求められるため、対策を考えておく必要がある。
- (レベル2)お酒は必要最低限の付き合いでよい(会食や催事などの場のみ)
こちらの場合もかなりハードルが高く、前項の①、③~⑤では飲酒欲求を抑制する必要がある。さらに、②についても不要な飲酒量や頻度を抑える事が求められるだろう。(飲みの機会に飲みすぎない方法の習得が必要)
基本的に主体的に飲みたいと思っているわけではない方が多いと思うので、極力飲まない方法を考える必要がある。
- (レベル3)お酒は大好きなので、最大限楽しみながら健康を維持したい
お酒が好きな方の大半は、最大限楽しみながら、健康を維持し、お酒のデメリットを最小化したいという事だと思う。こちらについては、どんな時に飲んでもよいと思っているのか、どのレベルまでが許容できるのか(二日酔いでもとにかく飲むときは、飲みまくりたい。基本的には明日に影響ない範囲で楽しみたい 等)を考える必要がある。
最後に(次回に向けて)
まずは、自身がお酒とどのように付き合うべきなのかを考えておく必要がある。既にお酒に依存してしまい、健康を害している場合は、専門の機関にご相談頂きたい。
次回以降、具体的にどのようにしてお酒との付き合い方を考え、うまくコントロール出来るようになるかについて考えていきたい。


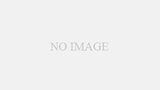
コメント